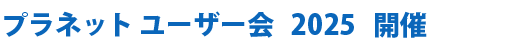過去の失敗を経てコロナ禍でDXを決断
社員をIT人材にリスキリング
私が取締役を務める松本興産(埼玉県秩父郡小鹿野町)は自動車部品を製造する、従業員280人ほどの中小企業だ。以前は非効率な作業が多いうえに部署間の風通しも悪く、またIT人材もゼロだった。さらには過去に約1500万円かけて導入した生産管理システムが結局使えなかったという失敗経験があり、DXに対する嫌悪感も社内では強かった。
しかしコロナ禍で業績が悪化し、人員削減や資産の売却もできない中で、お金をかけずにできることは何かと考えたときに残った選択肢が「DX」と「会計教育」であり、どうやってコストを削減して利益を出すかを社員たちに考えてもらうことだった。また、IT人材を新たに採用することもできなかったので、既存の社員をリスキリングすることにした。
中小企業は経営層の率先がカギ
性格診断で「ファーストペンギンチーム」結成
取り組むにあたって参考にしたのが「イノベーター理論」※だ。いきなり全ての社員の意識改革を行うのは難しいと考え、まず2.5%の社員がDXに着手し、次いで13.5%、34%……と段階的に社員を巻き込んでいく計画を立てた。
IT専門人材がいないような中小企業の場合、最初の2.5%には経営層が加わる必要がある。松本興産も過去のDXではIT推進課を作って経営層は報告を受けるだけだったが、兼任の担当者ではほかの仕事が忙しくなったときにDXが止まってしまう。そのため、現場に任せきりにせず経営層が主導することがカギになる。
最初に行ったのは、社内のExcelを全て印刷することだった。それぞれのセルに何の情報が書かれているかを洗いだし、受注関係、生産計画関係などのグループに分けて、複数部門で重複しているデータなどを調べた。2か月ほどかかる地道な作業になったが、その後のアプリケーションづくりの際に役立った。
次にどの社員をメンバーに加えるかを決めるために、全社員の性格診断を実施した。アメリカで開発されたPCM性格診断を使って「論理的」「創造的」「調和」「遊び心」「信念」「行動的」の6タイプに分け、最初に「論理的」「創造的」タイプの社員を巻き込むことにした。DXのためのアプリを開発する際、論理的タイプは筋道を立ててアプリの設計を考えることができ、創造的タイプはそのアイデアを形にするのに特性を発揮する。
「信念」タイプはリーダー向きで、当社でも役職者として活躍しているが、13.5%の中にはあえて入れないことにした。まずは不完全でもいろいろなDXのアイデアを出すことを重視していたので、完璧さを求めがちな信念タイプが、そのアイデアの火を消してしまう恐れがあると考えたためだ。
DXに対する社内の恐怖感をやわらげるために、この最初のチームは「DX推進委員会」といった堅い名称ではなく、あえて「ファーストペンギンチーム」というかわいい名前にした。
※ イノベーター理論:新製品などが市場に浸透する過程をモデル化した理論。イノベーター(2.5%)、アーリーアダプター(13.5%)、アーリーマジョリティ(34%)、レイトマジョリティ(34%)、ラガード(16%)の順に新製品などを受け入れるとされる
自作アプリで手作業を自動化
年間1万時間・1500万円を削減
はじめに意識したのは、「小さな成功体験」をつくることだ。アプリを作っている途中でも進展があれば、まだ改善点があると感じても「すごいね!」と褒め、「もっとやろう」という雰囲気をつくった。また、最初に制作するアプリには、社員の8割以上がかかわる業務に関係するものを選んだ。なるべく多くの社員に成果を実感してもらい、DXに巻き込みたいと思ったからだ。
こうしてできたのが「検査記録アプリ」だ。当社では自動車部品を毎月500万個出荷しており、それらを60人ほどの検査員が全て目視でチェックする。従来は、傷が何個あったかといった結果を一旦紙に記録し、後でExcelに転記していた。入力ミスで数値が合わなければデータを調べる必要があり、多大な時間を取られていた。この検査結果をアプリ上で記録・送信できるようにしたことで、年間1万時間以上、1500万円の削減につながった。
検査メンバーはほとんどが主婦の女性なのだが、検査記録アプリにはデータ送信すると何回かに一回「当たり」が出る仕掛けを加え、倉庫に置いてあるお菓子などの中から好きなものを選べるルールにした。DXのイメージを柔らかいものにするために、このような工夫も施している。
こうして成功事例ができると、「私でもDXができるかもしれない」という社員が出てくる。アプリを作る人が増え、社内に知見がたまると、相談し合いながらDXに取り組む環境ができてくる。次の34%には、全てのタイプの社員を巻き込んでいった。
誰も取り残さないDXを意識
空いた時間で新商品を生み出す
DXはスマホ世代には比較的なじみやすいが、長年働いている職人や、年配の検査員は「恐怖」を感じるかもしれない、という懸念があった。そのため、不安を感じる原因を取り除き、心理的安全性を確保することを重視した。
恐怖の一つ目は「取り残されるかもしれない」という不安だ。これに対しては「誰も置いていかないデジタル化」を目指した。アプリは一つの画面にボタンは二つか三つまでとし、誰でも迷わず使えるレイアウトにした。
二つ目は「人事評価が悪くなる」という不安。これに関しては、従来の評価制度は変えず、DXができないからといってマイナス評価にするのではなく、デジタル化に貢献した社員にプラスアルファで賞与を上乗せする仕組みにした。
そして三つ目が「自分の仕事がなくなるのではないか」という不安だ。業務が効率化されれば短い時間で作業が終わるので、確かに余力が出てくる。ただ、そのぶん人員削減するのではなく、新たな価値創造に時間を振り向けている。お猪口や箸、キーホルダーといった自動車部品以外の製品を試作しており、今後は実際に販売することも検討している。
「会計教育」でDXの納得度を高める
決算書を通して会社全体をマクロに俯瞰
DXを継続させるために、次に取り組んだのが社員への「会計教育」だった。
なぜDXと会計が関係するかというと、DXの目的を「生産性を高める」「効率を上げる」と抽象的に表現するより、具体的な目標数値を掲げるほうが、社員(特に論理的タイプ)の「腹落ち」度が違ってくるからだ。腹落ちすればDXが自分ごとになり、意識と行動が変わる。当社の場合、次年度が4000万円の赤字になりそうなところからスタートしたので、固定費を4000万円削減するという明確な目標があった。
また、DXを進める際には、組織を俯瞰して見るマクロな視点が必要だ。会社全体を見渡した上でどこをDX化するかを考えないと、部分最適で終わってしまう恐れがある。
そして、組織で起こっていること、モノや人の動きを金額に変換して表しているのが決算書であり、マクロな視点を持つには決算書を理解できるようになる必要がある。
財務諸表をイメージに置き換え
直感的に理解できる「風船会計」を考案
しかし、数字と文字の羅列である決算書を理解することは簡単ではない。当社でも以前から経理部が会計ソフトのデータをExcelに落として社内に共有していたが、実際に見る社員はごくわずかだった。
そこで、決算書の情報をイメージに変換し、誰でも直感的に理解できる「風船会計メソッド」を独自に編み出した。これは貸借対照表を豚の貯金箱に、損益計算書を風船に置き換えるものだ。現在ではStar Compassという別会社を立ち上げ、他企業のほか小中学校でも出張授業を行い、風船会計を広めている。
さらにイメージが湧きやすいように社員が作ってくれたアプリ上では、各製品を表す風船が利益率によって青・黄・赤で色分けされている。当社は限界利益率の目標を45%以上に設定しており、45%を割った製品の風船は黄色や赤になり、下に沈んでくる。「風船は浮かぶとうれしい、沈むと悲しい」という直感的イメージと結びつけ、画面上では利益率の高い製品ほど上に表示されている。下がっている風船を見た製造部員は「今まで100個の製品を作っていた材料から102個作れるようにして、材料費を下げられないか」、営業部員なら「お客様に価格転嫁をお願いして、100円の製品を103円にしてもらおう」などと考えることができる。
業務アプリの内製化で固定費を削減
利益改善やベースアップにつなげる
これらのアプリは「Microsoft Power Apps」を使って制作している。ローコードで簡単に作れ、サブスクリプションで安価に利用でき、元々使っていたExcelとの親和性も高いため採用した。
ほかにも出張精算アプリや棚卸しアプリなどを開発し、それまで使っていた既製のソフトを解約することで経費を削減していった。経理ソフトで年間180万円、情報共有ソフトで360万円、グループウェアシステムで50万円を節約できた。また、従来は大量の紙を使って作業していたので、その経費と作業にかかる人件費だけで3600万円を削減できた。
従来は定型業務が3万時間以上あったのを、9500時間まで短縮することができた。コストを減らせたことで2024年は売上総利益が前年比で236%アップし、4.7%のベースアップを実現した。2025年も約5%のベースアップを行っている。
業績が改善したことも良かったが、私はそれ以上に、「田舎の下請企業でもやればできる」という社員の自信と自己肯定感につながったこともうれしかった。
デジタル化により働き方改革が進展
利益増で福利厚生も充実
DXが進んだことで働き方改革も可能になった。特に子育て中の時短勤務社員などによる在宅ワークの幅が広がったことが大きい。それまでは紙のファイルが会社にしかないため出社する必要があった業務も、パソコン一つあれば自宅からでもできるようになった。
また、従来の時短・在宅ワークの社員は業務がルーティンワークに限られがちだったが、アプリ制作は自宅でもできるので、作ったアプリがほかの社員から喜ばれると、充実感や成長を実感できるようになった。内製化したアプリは自社の業務に合わせて自由にカスタマイズできるので、既製のソフトよりも使いやすいとベテラン社員からも好評だ。
私たちはDXを始めたときから、目的は効率化ではなく、社員を幸せにすることだと考えてきた。固定費が削減できて利益が出るようになると、「幸せ」のための支出に還元できるようになる。
既に紹介したベースアップやプラス賞与のほかにも、医療費として、がん治療中の社員に年間100万円を支給している。また、工場横にオフィスガーデンを整備し、バーベキューをしたり、ハーブティーを飲みながら打ち合わせをしたりできるスペースになっている。
ここでお話しした事例により、日本DX大賞や埼玉DX大賞などで賞をいただき、各地で講演にも呼ばれるようになった。
私たちのような地方のIT人材ゼロ企業でもDX企業になることができたので、皆様の会社でも、より一層DXを進めていただければ幸いである。