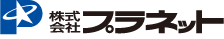万、已むを得ず (幸田真音著、PHP研究所)
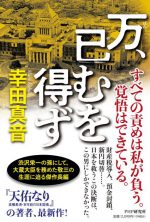
渋沢栄一の孫の渋沢敬三(1896~1963年)の物語である。
渋沢栄一は一万円札の顔となり、知らない人はいないという偉人である。その栄一の長男は渋沢家の事業を継ぐ気はなく、栄一の眼鏡にかなわず、一時は廃嫡(はいちゃく)されてしまう。栄一は、利発な少年であった孫の敬三に期待をかける。しかし、敬三は生物学に興味があり、長じては民俗学に傾注するほどであるから、経営や経済には興味がなかった。だが、栄一の必死の説得で、渋沢家の事業を継ぐことになる。このあたりは、NHKの大河ドラマ『青天を衝け』にも描かれていたので、ご存じの方も多いことだろう。
敬三は、祖父の頼みに逆らえず、渋沢家を継ぐことにし、東大の経済学部に入学する。卒業後は、横浜正金銀行に入行し、ロンドン支店に赴任し、約3年間勤務した後に帰国。早速、栄一が創立した第一銀行の取締役に迎えられる。1941年に第一銀行の副総裁に就任した直後、今度は日本銀行の副総裁になるよう要請される。そして、更に1944年には日銀総裁に就任することになった。とんとん拍子の出世であるが、時は戦争の真っ最中である。
日本各地に焼夷弾を落とされ、焼け野原になり、おまけに広島と長崎に原子爆弾を投下され、日本は1945年8月に全面降伏した。その2か月後、幣原(しではら)内閣が発足する。幣原(しではら)喜重郎(きじゅうろう)総理から敬三は大蔵大臣になるよう頼まれる。幣原(しではら)家は敬三の母の妹の嫁ぎ先、つまり、親戚である。やむなく敬三は大蔵大臣に就任する。日本の歴史上これほど困難な時代はなかった。その時の大蔵大臣である。
破綻に陥っていた日本の財政を、どのようにして立て直すか。この時、有名な経済学者の大内兵衛が敬三に向かって、非常の時なのだから、蛮勇をふるえと、熱くアドバイスをする。大内兵衛は東京大学経済学部で財政学の講義をしていた。敬三はその教え子である。
様々な検討の末、財産税を課すしかないという結論に至る。国家存亡の危機である、富裕層に大きな負担をしてもらうしかない。戦争に負けて国家財政が破綻しても、多くの資産を保有している富裕層はまだ多く、旧華族あるいは戦争成金達も多くの財産を残している。天皇家も徳川家も例外ではない。もちろん渋沢家も多額の財産税を支払う覚悟である。
通常の税は、所得や利益に課すのであるが、財産税は保有する財産に課する税である。それには、誰がどれだけの財産を持っているかを捕捉しなければならない。そこで、敬三は先ず預金封鎖をし、更に新円切り替えをすることとした。新円にすることで、旧円で隠し持っている財産を炙り出すためである。
これら一連の対策を遂行するには、GHQに合意してもらわなければならない。その交渉の経緯など、本書の後半でドラマチックに記述されている。
ところで、敬三は民俗学でも大きな足跡を残している。自宅の車庫の屋根裏に、多くの資料を保管しアンチック・ミューゼアムとして、仲間を集めて研究をしていた。この研究資料は神奈川大学の常民文化研究所に引き継がれている。
実は、私の父が渋沢敬三の民俗学調査に同行していたのである。そのため、父は渋沢敬三と面識があり、父から、たびたび渋沢敬三についての話を聞かされていていた。数年前に、神奈川大学の常民文化研究所の方が、渋沢敬三の調査資料の中に玉生道經撮影という写真資料があるということを教えてくれたため、本当に敬三の調査に父が同行していたことを確認できた。
父の話では、「これで渋沢家はおしまいだ」と言っていたということである。自ら遂行している財産税では率先して財産の多くを差し出さざるを得ない立場である。旧華族は、多くの土地や建物を処分して税金を支払った。徳川家は、港区芝の徳川家の墓所である増上寺の土地の一部を売却して支払っている。いま、そこにはホテルが建っている。
「これで渋沢家はおしまいだ」と言っていたことは、本書でも書かれている。確かに、祖父・渋沢栄一が設立した500社もの会社は存続したものの、渋沢家が保有した株はほとんど放出し、渋沢財閥は消滅してしまった。
戦後復興の大恩人は渋沢敬三だというべきであろう。