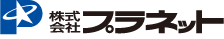シュガーマンのマーケティング30の法則 (ジョセフ・シュガーマン著、フォレスト出版)

アメリカで、よく売れた本だということである。
内容は、マーケティングというより、営業現場の手練手管の事例集のような本である。著者シュガーマンの自慢話がたくさん記載されている。
著者が学生時代に、大学のクラブに新入生を勧誘する際、彼が行った方法について自慢している。セクシーで美形の女性をそろえて、新入生たちを勧誘するのが有効だと考え、なんと、彼は近くのストリップ劇場の女性を連れてきて、勧誘に当たらせたということである。大学のクラブへの勧誘はクラブに所属する上級生が行うのが普通である。これは相手をだましたに他ならない。
いかにして、ユーザに思い込みをさせることに成功したか、いかにして、競争相手を出し抜いたかという自慢話が続いている。
また、誠実であることが大切であるとも書かれている。確かにそのとおりである。しかし、よく読んでみると、相手に誠実であると思われることが大切だと言っているようだ。
お客と商談の時に最初の挨拶のあと、天気の話から始め、世間の噂話しなどを交わすのだが、その際には、相手に否定的な返事をさせないように話しかけなければならない、ということはよく言われている手法である。本書でも同じような話法が具体的に記されている。少しは参考になる。
それにしても、アメリカのセールスマンたちは、この本を参考にして営業をしているのだろうか、だとしたら、消費者は本当の満足を得ることはないだろう。
なにしろ、商談時の演出や話法で、売れればいいのであって、消費者が購入した後、後悔しようが、一回使ってやめてしまうことになろうと、どうでもいいように読める。その商品について消費者がどのように思ったか、使い勝手はどうなのか、こうした情報が、その商品を作った人(メーカー)にフィードバックされることはないだろう。そうすると、消費者が本当に満足するように商品の改善が行われることはない。
流通機構の社会的責任などは、まったく意識していないようである。これでは、社会はよくならない。しかし、シュガーマンに言わせれば、自分には社会をよくする義務はない、自由に商売をすることによって、競争が生まれ競争の結果市場がバランスするのだ。これが自由市場主義経済というものである、と言うことだろう。
昨今、自由主義経済の限界が指摘されているが、ここにその一端が垣間見られる。