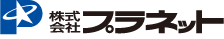ハチは心をもっている 1匹が秘める驚異の知性、そして意識 (ラース・チットカ著、みすず書房)
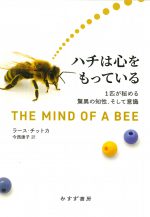
以前、紹介した『裏山の奇人‐ 野にたゆたう博物学』の著者小松貴は、ハチを手なずけて遊んでいたということである。掌にコオロギをのせて、待っているとアシナガバチがやってきて、手の上でコオロギを肉団子にして持ち去る。さらに、もう一度やってきて残りの肉を団子にして運び去る。また後日、その場に来ると、そのハチが覚えていて、寄ってくるということである。ハチの識別能力、記憶力はかなり高度なものであると思われるわけである。
ハチは独自の進化を続け、相当高度な知的能力を持っているのは確かなことのようだ。本書によると、ハチの認識は、独自の感覚で人が知覚できない信号を感知して、反応しているということである。特に、位置を感知する能力に優れているということが分かっている。そして、ハチが餌を探して、それを仲間に伝えるためにダンスをして情報の共有化をすることは、以前から知られていることである。
ハチは、どのように空中を飛んで餌を探し、それを巣に持ち帰るのだろうか。
アリは複雑に歩き回って餌を探し、見つけると、歩いてきた道をたどるのではなく、まっすぐに巣に向かう。アリの場合は地面を歩くので観察すればこの行動を把握することができた。しかし、ハチの場合は、空を飛ぶので行動を把握することができなかった。
近頃は動物に発信機を取り付けて追跡することが行われている。サバンナを移動するライオンの首に発信機を取り付けて行動を観察することはよく行われている。しかし、ハチに重い発信機を取り付けることはできない。
ところが、イギリスの研究者がハチを追跡する装置を考案した。わずか15mgのトランスポーターをハチの背中に取り付け、それにマイクロ波を照射し、返ってくる電波を受信するという、レーダー追跡装置を開発した。この装置で観察したところ、ハチも、アリと同じように餌を見つけると、一直線に飛び帰ることが分かった。
犬や猫を飼っていると、それぞれに個性があることは、誰でもが知っているところであるが、規格化された大量生産品のようにたくさんの子供を作る昆虫が、それぞれに個性を持っているということは考えられないことだった。しかし、それぞれに個性を持っていることが分かってきた。本書のハチの観察以前には、クモの観察で、それぞれのクモの巣の形に個性があることが報告されているそうである。レーダー追跡装置での観察でも、個々のハチで少しずつ行動の違いがあるのが分かったそうである。
ハチの巣の入り口での行動を観察すると、自分の大きさに応じて出入りするということである。つまり、自分の大きさを分かっていて、自分が自分であることを知っている。言うなれば、自我を有していて、心があると考えられるわけである。
以下は、本書にない考察である。
太古の昔から、ハチはハチ、人間は人間の進化を続けて今の姿になったわけだが、それなりの能力を身に着けて生存しているわけである。空を飛ぶという能力を身に着けるのに、あるいは、花の奥の蜜を吸いとる口吻を獲得するのに何百万年もかかったのだろう。マダガスカルのアイアイという小型のサルは、木の実の中身を掻き出すだけのために中指を異常に長く進化させた。そのために何万年もかかったに違いない。
しかし、人間は飛行機という道具を作り出し空を飛ぶ能力を獲得し、スポイトという道具を作れば蜜を吸いとることもでき、鉄で細長い匙(さじ)を作れば実を掻き出すこともできる。自己の身体を進化させ機能を身に着けるのと、道具を工夫して能力を得るのとでは、とてつもなく大きな違いである。人が空を飛べるようになってわずか100年、鉄やガラスを利用できるようになってから2000年ほどである。
その結果、人間は地球を支配するようになり、地球資源を大量に掘り出し、他の生物を利用して、さらなる進歩を続けている。100年前の人口が40億人、現在は80億人と異常な増殖をした。
もうそろそろ、人間も含めた地球の生物のあり方について、本気で考えなければならない時に来ているようだ。