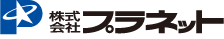日本神話の考古学 (森 浩一著、角川新書)

著者の森浩一(1928~2013年)は、生涯をかけて日本の考古学と古文書学を探求した学者である。小学生のときに土器片を見つけたことをきっかけに考古学に興味を抱き、以後、多くの発掘調査に携わり、様々な考察を重ねてきた。また、『魏志倭人伝』をはじめ、『古事記』と『日本書紀』(以下「記紀」)、さらに『風土記』などの研究も進め、説得力のある見解を数多く発表している。
考古学や古代史については、権威主義が蔓延している。本書にも書いてあるが、「神武(じんむ)東征(とうせい)」について論じると、科学的ではないとの批判を受けることが多かったということである。
「神武東征」について、本書では実証的に論じ納得性の高い解説をしている。イワレ彦(後の神武天皇)が東に赴いた航跡を、記紀に基づいて辿っている。イワレ彦の船団は、豊のウサ(宇佐)、筑紫(ちくし)のオカ(岡・遠賀(おんが))から安芸(あき)、吉備にも立ち寄り、難波(なにわ)の海に向かう。当時は深く入り込んでいた大阪の湾を生駒山付近に進むと、ナガスネ彦と遭遇し、戦いになる。ナガスネ彦と戦った場所は“草(くさ)香(か)”となっているが、その地名は、東大阪市日(くさ)下(か)町として残っている。ナガスネ彦との戦いで、イワレ彦は敗れ、船に逃れて紀伊半島沿いに南下して、紀伊半島南部の丹敷(にしき)浦に上陸する。現在の三重県紀勢町錦(にしき)と比定される。その錦付近では、今でも神武天皇が上陸したことを祝うギッチョ祭りが行われていることを、驚きをもって記述している。
上陸したイワレ彦は、陸路を進み、吉野を超え奈良盆地に到着する。イワレ彦は、再びナガスネ彦と戦い、今度は勝利する。イワレ彦は、奈良盆地を平定し、大和の国を創立し、初代の神武天皇となるのである。
記紀に書いてあるこの「神武東征」は、多くの地名が一致していることから、事実を述べているものと考えられるのに、神話に過ぎず研究に値しないとする権威主義的考古学には困ったものである。
やはり、文献だけではなく、現地に行って検証することが重要である。著者は、20歳の頃(1947年)に対馬と壱岐に渡って現地調査をしている。言うまでもなく魏(ぎ)志(し)倭(わ)人伝(じんでん)に記されている対馬の国と一支の国である。対馬の国は対馬、一支の国は壱岐の島であることは、異論がないところである。この2島を森浩一は1947年に訪れて、地元の郷土史家に会うなど、実地調査をしている。1947年の対馬と言えば、まだ戦後の混乱が残っており、島の上空は米軍の飛行機が飛び交っていた時期である。すごい行動力である。
著者は2013年にお亡くなりになっているが、本書は2025年の出版である。これは、1999年に出版された朝日文庫を改定したものである。やはり、森浩一の見解は多くの人に受け入れられているからであろう。早くも、第4版を重ねている。
ところで、森先生がお亡くなりになった後の2023年に、富雄丸山古墳から前代未聞の2メートルを超える長尺の蛇行剣が出土、更に前例のない盾型の大型銅鏡も発見された。この富雄の古墳から生駒山を超えたところが、ナガスネ彦がいたクサカである。現在は近鉄奈良線の富雄駅から生駒トンネルを抜けてすぐに東大阪がある。この位置関係をどう解釈すべきか森先生の見解をぜひ聞きたかったものである。