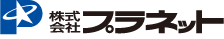壁とともに生きる わたしと「安部公房」 (ヤマザキマリ著、NHK出版)
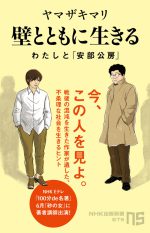
ヤマザキマリは漫画『テルマエ・ロマエ』の作者である。中高年の中には、漫画は見ないという人もあるかと思うが、『テルマエ・ロマエ』は映画化され、テレビでも放映されたので、知っている人も多いことだろう。
ヤマザキマリは17歳でイタリアのフィレンツェに絵画修業のために留学、イタリア人の詩人と同棲するのだが、貧困に陥ってしまう。食べるのに困るほどの貧乏であるにもかかわらず、キューバにボランティアに出かけるなど、エネルギッシュで活動的な女性である。そうこうするうちに、子供ができる。ヤマザキマリは、稼ぎのない詩人と子供の二人を養うことは不可能と考え、詩人と別れる。
別れたものの、相変わらず貧乏で、何とか生きる道を探り、行きついたのが漫画を描くということだったそうである。そして、書いたのが『テルマエ・ロマエ』。ヤマザキマリのイタリアをはじめ幅広い知識と国際感覚が、作品に厚みをもたらしているものと思われる。つまり、『テルマエ・ロマエ』は、テーマを決めた後で、様々なことを調べて制作しているのではなく、すでに知っていることをまとめて作品にしているように見える。旧ローマ帝国の版図であった地中海、エジプト、中東で暮らしたことがあり、そこで見聞きした体験をもとに制作しているのだろう。
さて、本書であるが、全編が安部公房を紹介する内容である。ヤマザキマリはイタリアで絵画の修業をしていたころ、芸術家仲間からイタリア語の『砂の女』(安部公房)を手渡され、読むように勧められた。イタリア語のこの本を、辞書を片手に読み、すっかり魅了されてしまう。日本にいる母親に連絡して安部公房の作品を送ってもらい、片っ端から読んだということである。
本書の半分ほどが安部公房の代表作『砂の女』の紹介となっている。昆虫採集に出かけた主人公が砂の壁から転落して、下に住んでいる女の家で生活を始める。砂の壁に囲まれ、這い上がることができない、いわば蟻地獄の底に落ち込んだ状態である。
主人公は、新種の昆虫を見つけて命名権を得て、自分の名前を後世に残したいとの世俗的な欲を持っている。それに対して砂の壁の下に住んでいる女は、世俗的な欲は全くなく、ただ生きている虫のよう。そこには大きな壁があるというわけである。
安部公房の『砂の女』は、映画化もされて、ノーベル文学賞の候補にもなった。本書には、『砂の女』の他に『終りし道の標べに』、『けものたちは故郷をめざす』などなども紹介されている。
ヤマザキマリはイタリアに住み、時々日本に帰ってくるという生活をしていたのだが、日本に滞在中にコロナが蔓延して、海外に出られなくなってしまった。そのため、日本滞在が長くなり、日本のメディアに登場することが増え、人気が出るようになった。
今の日本は安全で居心地がいいため、その中で安住している日本人が多い。砂の壁の底に住み続けている砂の女のようである。壁の中に閉じこもりがちの日本人が多い中、ヤマザキマリは世界に雄飛している。この女性の逞しさには、感服する。