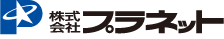世界の賢人と語る「資本主義の先」 (井手 壮平著、講談社)
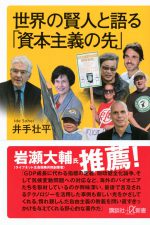
現代の資本主義が、地球資源の大量採掘を続け、地球温暖化をもたらしていること、また、大きな格差をもたらしていること、などを問題とし、新しい資本主義を模索する議論が盛んである。
アダムスミスらが唱えた経済活動の自由が、経済を活性化させ産業革命をもたらした。しかし、経済の大規模化とともに大きな資本を必要とするようになり、資本家と経営者と労働者という階級が明確になった。また、経済の大規模化は、多くの工場を作り出し、そこでの生産は見込み生産であったため、景気変動をもたらすことになった。景気変動は、年々その振幅を広げ、とうとう世界大恐慌を引き起こした。
ケンブリッジ大学のケインズが、大恐慌の際に失業者を救済するために政府主導による事業を起こすことをアメリカの民主党のルーズベルト大統領に提言し、これが採用された。しかし、これに猛反発する人たちがいた。市場原理を絶対とする新自由主義を唱えるシカゴ大学の学者たちである。政府が事業をするなどと言うことは市場原理に反することで、政府はあくまでも金利の操作など金融によって経済の調整をするべきだというマネタリズムを唱えた。
新自由主義のマネタリズムは、共和党のレーガン大統領が受け入れ民営化、貿易自由化、金融自由化を掲げて、小さな政府政策を始めた。こうした政策が、いわゆるワシントンコンセンサス(世界銀行・IMF・米政府の合意)となり、これがグローバルスタンダードであると、世界各国に同様な政策をとることを求めた。これによって、何でも市場に任せるという市場原理主義が当たり前となり、強いものが勝ち続ける経済体制となり、格差拡大が顕著になった。
本書の第3章で、民営化について論じている。パリ市の水道事業を民間企業に任せたら、水道料金が3倍になってしまったことを事例にして、あらゆることを市場に任せるという市場原理主義には、問題があることを指摘している。民営化すると、株主と経営者と労働者、そしてユーザーがいるという構造になる。事業としては、安全な水を安定的に提供することが目的で、経営者と労働者はそのために努力をする。しかし、株主という投資家は、投資の見返りが第一の目的であるため、経営者にコストの削減と利益の増大を求める。投資家は、配当さえ多くもらえれば、どんな事業でもいいのであって、水道事業に使命感を持っているわけではない。
シカゴ学派のハイエクは、水も空気も自由市場で取引するべきだと、いわゆる市場原理主義を唱えていたが、その後、哲学者になり純粋理論を追求した学者である。やはり、公共性のある事業までも自由市場に任せるのは無理があるようだ。
ギリシャの財務大臣を務めたことがある経済学者ヤニス・バルファキスは「すべての経済学は間違っている」と言っている。
本書は、バルファキスなど多くの賢人に、あるべき姿を尋ねているが、残念ながら 決め手がない。これからの人類は、模索を続けながら、是正を重ねていくしかないようだ。