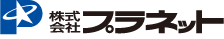裏山の奇人:野にたゆたう博物学 (小松貴著、幻冬舎)
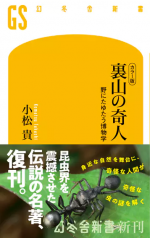
本屋で立ち読みをしていたら、おもしろい本を見つけた。
パラパラと読んでみたら、子供のころの小松少年は、アシナガバチを手なずけて遊んでいたと書いてあった。捕まえたコオロギを手の上に乗せ、アシナガバチに差し出すと、ハチは手の上でコオロギを持ち運べるサイズの肉団子にして持ち去り、さらに、残ったコオロギを取りに戻ってくる。その後も、ハチは小松少年を覚えていて、何度もハチが寄ってくるようになったということである。ファーブルの「昆虫記」を想い起こさせるような文章だ。
小松少年は、裏山でハチを相手にしたり、石を裏返して蟻を観測するなど一人で遊んでいたということである。このように、一人で裏山で遊んでいたため、人嫌いだと書いてあるが、文章を読むとユーモアもあり、人に対する配慮も感じられるので、適合性がない変人ということではないようである。
長じて小松氏は信州大学に進学し、昆虫研究の専門家になる。その専門は、「好蟻性生物」の研究ということである。蟻は世界各国に大量に棲息している。そして、そのアリに依存している生物が無数にいるそうだ。アリの巣に入り込んで生活するもの、アリを餌にするものなど、実に多様だということである。アブラムシがアリに保護され、アブラムシが生み出す蜜をアリが好んで食べるというのはよく知られていることだが、その他にも、多くの生物がアリと様々な関係を持って、生きているということである。
植物を食べる植食昆虫は植物の毒抜きをしてから食べる。獲物を神経毒で麻痺させてから利用するハチ。などなど、おもしろい話がたくさん載っている。昆虫好きでなくても、読んでいて面白い。話のネタになりそうである。
著者の小松はアジアや南米に調査に赴き、あらゆる好蟻性生物を見つけ出し、その生物が共生するアリの種類も分別するという研究を続けているが、その費用が多額のため貧乏生活をしているということである。本書によると、米が買えずに麦を主食にしているそうである。
ファーブルも赤貧に甘んじていたということであるが、このような研究者は、収入の道が少なく、困窮している人が多い。昆虫の研究は、確かにお金にならないのだが、地球環境の持続のためには、誰かが研究をしなければならないことである。何とか研究者を支援をしてあげたいものである。本書には、研究の成果をまとめた「好蟻性生物図鑑」を出版して収入を得たいと書いてある。その夢は2023年に『アリの巣の生きもの図鑑』としてすでに出版され、好評を博している。
実は、ファーブルの晩年は、「昆虫記」が売れ始め裕福になったということである。小松氏も、本書のような一般向けの本が売れるようになりそうに思える。