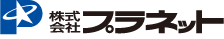SDGsエコバブルの終焉 (岡崎 五朗, 田中 博ほか著、宝島社)

近ごろ、欧州におけるEV(電気自動車)の売れ行き低迷が続いている。EVは、充電に時間がかかる、低温では極端に性能が落ちる、バッテリーには寿命があり、8年ほどで交換しなければならないこと、などによって消費者に嫌われて、売れなくなってしまったのである。EUを中心にエンジンを全面的に禁止して、二酸化炭素を排出しないEVにするという欧米諸国の政策が裏目に出始めているわけである。そもそも、すべてをEVにしようという政策には問題があったと言うしかない。
かつて、燃費のいい日本の車が売上を伸ばし始めると、欧州の自動車業界がCO2の排出量が少ないのは、ディーゼルエンジン車であるとのキャンペーンを始めた。そもそも軽油を燃やすディーゼルエンジンが環境に良いとは思われない。日本のハイブリッド車を否定するための意図的なキャンペーンだったと考えられるわけだが、2015年にフォルクスワーゲンのディーゼルエンジンのデータ捏造が発覚して頓挫してしまった。そして、今度はEVだというわけである。
EVは大きくて重たいバッテリーを搭載しなければならない。バッテリーには希少金属を用いる必要があるのだが、「EV1台に使う原材料でプラグインハイブリッドなら6台、ハイブリッドなら90台生産できる」とのトヨタの試算は説得力がある。
EVは、製造時にガソリン車をはるかに上回るエネルギーを消費する。バッテリーを廃棄するときには、毒性物質の処理や高コストなリサイクル技術が大きな壁となっており、大量の廃バッテリーが今後社会問題となる可能性も指摘されている。それを、走行時のCO2排出量だけでEVの普及を推進することは、本質的な課題を無視した無責任な議論と言わざるを得ない。
欧州の全てをEVにするとの政策に、悪乗りしたのは中国で、今後EVになるとの見通しにすべてを賭け、大量のEV製造を開始、安い価格で輸出を始めた。これに慌てたのは欧州の自動車メーカーである。EVが良いのだというキャンペーンを続けていたら、中国からの輸入がさらに増えてしまう。このままだと、ヨーロッパの自動車業界としてはまずいことになってしまう。
第3章では、環境原理主義に異を唱え、欧米の環境原理主義者は科学的事実を捻じ曲げていると論じている。「科学はうそをつかないが、科学者はうそをつく」とまで言っているので、かなり激しい。
日本は、GDP当たりの原油消費量は先進国の中で低い国であるのに、日本の発電について糾弾する人たちがいる。欧米の人は、自分たちが世界のルールだと思っているのだろうか。
環境にもっとも悪いのは戦争である。1キロ/リッターしか走らない戦車、大量のCO2をまき散らすミサイル、環境破壊そのものである。環境が何よりも大事ならば、戦争を止めるべきである。
環境第一主義が盛んな今日、かなり大胆な本である。しかし、双方の見解を冷静に判断して、今後の在り方を真剣に検討すべき時に来ているようだ。